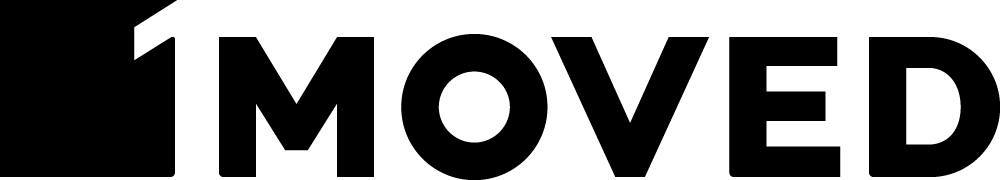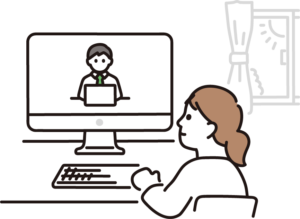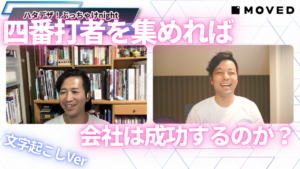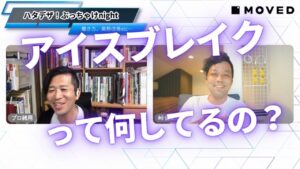善意は破綻する/ハタデザ!ぶっちゃけnight
この記事では、「 善意は破綻する 」というテーマを掘り下げています。
善意だけでは長期的な成功が難しいと指摘し、その背後にある要因も考察しています。これは仕事や日常生活での人間関係にも関わる問題です。
ぶっちゃけnightとは
働き方トレーナー・峠 健太郎、プロ雑用・小林 信也が、働くということの本質について語る番組です。
 小林
小林今回のテーマは「 善意は破綻する 」です。



「 なんかあの人の頼みは断れないな 」とかありますよね。



このポイントは2つあります。
1つはタイトルの通り「 善意は破綻する 」です。
もう1つは「 それって本当に善意なの? 」です。
1つ目「 善意は破綻する 」



皆さんもあると思いますが、人に良かれと思ってやっていることが、後々「 あれで良かったのだろうか 」となることですね。
一番端的な例は、10年前ほど、リタイアした人たちの間でNPO法人やボランティア団体を立ち上げるのがブームになってました。
そこからしばらく経ってブームが落ち着いたころに、それらの団体がどうなったか追いかける番組を見ましたが、大体組織運営が破綻しかけている、または破綻したところが多かったですね。
何で最終的に揉めているかというと、大体はお金の問題だったんですよね。
要するに、彼らはリタイアした後でも世の中に貢献したいという善意で立ち上げてると思うんですけど。
そのような活動が立ち行かなくなることが往々にしてあるわけですね。
それってなぜなのかと考えると、私はベースが善意しかないからと思いますね。



なるほど「 善意しかない 」ですね。
これは大きいポイントかもしれませんね。



僕、ボランティア団体みたいな任意団体で、一番素晴らしい活動してると思ってるのは、コミケの運営委員会ですね。
今はわからないですけど、昔は皆さん無償だったんですよね。
有志が集まってイベント活動とかをちゃんとやっていると。
巨大なイベントなんですけど、それをボランティアだけのスタッフで全部回してるんですよ。



その規模を無償でやってるって、すごいですね!



もちろん、活動費とかをちゃんと稼がなきゃいけないですが、それを目当てにはしてないですよね。
善意以上に必要なものとは



考えてみたら、うまくいく団体は善意以上に使命感にあふれてるんですよね。
そういう部分がないと、全員だけだとやっぱり維持するのは難しいんだろうなと思うんですよ。
何か製品だとかそういうものを、なんか原価で、原価近くで下ろすみたいな。
ビジネスの面でも、何か製品とかを原価近くで下ろすみたいな企業ありますよね。
でもそれが世界に出て戦えるような規模の企業になるかって言うとそんなことないんですよね。



外でこじんまりとした商売してるイメージあるんですね。



そういう部分でも、一時期の善意はいいと思いますが、継続するってことを考えると善意だけだとダメなんですよね。
善意以上の何かがないと継続していかないですね。
2つ目「 それって本当に善意? 」



さて、いいタイミングなのでテーマが移り変わりますが、もう一つのテーマ
「 それって本当に善意なんですか? 」ってところがあるんですよ。
特にバックオフィス部門とか、社内ヘルプとかを担当してるような人とかが多いと思いますが、非常にみんな善意にあふれる人多いんですよ。
でもそれゆえに、全部一人でなんでもいいよとやってしまい、抱え込んじゃう人とかもいますよね。
ボランティア精神と組織の危険性



中には本当に善意でボランティア精神にあふれていて、それをやってる人もいますよね。
それはそれで素晴らしいことだと思うんですよ小林
ただ、組織としては危険極まりないことだと思うんですよ。
中身がブラックボックス化してるってことは、
その人が事故にありましたとか、なにか事情で退社しましたとなると、
もう途端に崩壊するわけじゃないですか。



その人がいなくなったらどうするんですか?というのは、それって本当に善意なんでしたっけ?という事ですね。
善意と捉えられているだけの場合



もう一方で、別に善意じゃなくて、人に教えるより自分でやった方が早いな、ってやっちゃう人もいるじゃないですか。
これは善意と同じぐらい危険ですよね。
やはりブラックボックス化してしまう。
「 あの人いい人だよね 」って言われてるんだけど、実は本人としては全員じゃなくて、人に教えるのがめんどくさいと思ってるだけな人もたくさんいるわけですよ。
で、継続的に行なう必要がある活動については、
善意はむしろ邪魔になるパターンが多いんですよね。
一過性の善意と継続的な善意



たとえば、道を聞かれましたってときに、
丁寧に教えてあげる、連れてってあげる、感謝されるっていうのは善意で十分いいと思うんですよ。
だったら、それを永遠に続けますかっていう話なんですよね。
それって、永遠に続かない一過性のものだから、皆さん善意をもって対応するわけですよ。
電車で席を譲るのもたぶん同じなんですよね。
一時的なそのときの問題だから、善意で譲ることはできるんだけど、常に立っていなさいって言われたら困るよてって話ですよね。
「 あなたは善意で席を譲ったんだから、もうその善意をもって、そもそも席を座ることやめましょう 」とか言われたら、え?ってなるじゃないですか。
こういうことって世の中に溢れていると思ってて、例えば駅のエレベーターとか善意が破綻しかけている一例だと思います。
バリアフリーいいことだから推進していこうってやってますよね。
ただ、広い階段とエスカレーターが併設されたら、皆さんどっち使います?明らかにエスカレーターの方が混んでるんですよ。
もともとエスカレーターとかエレベーターだとかって、足の悪い人などのために設置されてるじゃないですか。
でも駅とか見てくださいよ。
何にも健康的に被害がなさそうな人たちがエスカレーターとか積極的に使ってません?



使ってますね。



結局みんな歩かなくなってしまう。
長い目で見ると健康被害が起きてしまうかもしれませんね。
これって本当に善意なのかと。
大多数の人は、それをバリアフリー化みたいなところで良いこととしているけど、長い目で見ると、それって本当に行うべきもんだったんだろうかって話があるんですよね。
このようなことが、世の中には結構いっぱいあるねって思うんですよ。
いろいろなことが、善意を持って弱い人に合わせてるゆえに、
全体に不具合が起こってくるとか。



これは確かにね、仕事でもありますよね。
聞かれたから教えたけど、そのメンターの人たちとかが、「 これは自分でやって欲しかったし、覚えて欲しかったのに、なんで教えたん 」みたいなところは遭遇したことはありますよね。
他の人が「 それやってあげようか 」みたいな善意でね。
善意の闇



まあ必ずしも、善意って人のことを考えているようで、
実は大元には、もっと深い闇が控えているのでは思うんですよ。例えば、その善意を使っている自分が好きであるとか、その善意を使っている自分が褒められたい、あるいは責められたくないっていう。
僕、世の中の公共施設のバリアフリーって結構それあるなと思ってるんですよね。
やらないといけない空気感で、やらないと責められるから、やっておこう的な。



ニュースになって問題になったから、『 早速うちは回避するためにやる 』とかは確かによく見ますね。



だからそれは一過性の見せかけの善意なんですよね。
でも善意は本当に一過性で一瞬だけ使う分にはいいんですが、継続できないんですよ。
継続的に行うためにはあんまり好用はないんですよね。
善意を受ける側もそうなんですよね。
善意ある人に毎度毎度善意をかけられたら、それ感謝しなくなるっていう。



「 前回は善意でやってたんだけど、なんで2回目3回目も当たり前のようにやらなきゃいけないんだっけ? 」
みたいな愚痴ってよく聞きますよね。
結局ね、自分をよく見られたいだとか、自分が攻撃されたくないだとか、そういう自分の身を守るために善意という名の皮をかぶせている人が結構いるんじゃないのかなって思うんですよ。



それは、頼まれ事した時に、別に自分がやらなくてもいいけど、断ったことで渋い顔されたらこっちが嫌やしとか、後からなんか言われたくないからっていうのを思うときがありますね。



から心底から溢れてくるような愛あふれた善意ではないんですよ。
それは優しさでもないし、善意としても良くない善意なんですよね。



偽善みたいな。



そうですね、偽善と言ってしまうのはあれなんですけど、僕は、やらない善意よりもやる偽善だと思ってるんで。自分が良いと思ったことをやればいいと思ってるんですが、それを自分が良いと思ってやるんだったら徹底してやらないとダメだよねって思います。
1回目善意で受けたことを、2回目3回目になってもうちょっと相手は私のことを考えてほしいなみたいなのは、かなり自分勝手だなと思ってるんですよ。だったら最初からやらないほうがいいなって。
最初の方に話したNPO法人とかもそうだと思うんですよ。
あんまり深く考えずに行動をやっちゃったんだろうなって。
で、それを継続させようという強い意思も感じられないってところが、僕は番組を見てて思いましたね。



最初は良かったんでしょうけどね、ほんとに。



やっぱり人ってピンチになったり不利になった状況の時に初めて本質が現れるので。
調子のいい時なんか、波に乗ってる時なんか、いくらでも善意発揮できるんですよ、人間は。自分がどうしようもなく苦しい時に、与えられる善意が本物の善意なんですね。



本物の実力もそういう時に出ますもんね。



だから善意は破綻するんですよ。継続できないですよね。



破綻っていう表現がまた面白いですよね。
最初の瞬間的な部分に関しては、もちろんそれで成り立つだけの時もありますが、何回も積み重なると崩れていく言い方なので、まさに言い得て妙をすごく感じますね。
善意より欲望の方が継続する



この話、逆に言えば、僕は悪意の方が継続率は高いんだろうなと思うんですよ。



確かにそうかもしれないですね。
その方が破綻しない感じがします。
悪意が破綻ってのは確かに想像しづらいですね。



悪意っていう言い方だとちょっと過激かなと思うものの、例えば自分をより良く見せたいとか、欲望みたいな。
それって自分の心の中から溢れてる欲求じゃないですか。そっちの方が継続しそうじゃないですか?
だから人がなにか成し遂げて結果を残すものは、決して善意ではないんですよね。やっぱ欲望とかの方なんですよ。



これ見極めが難しいですね。小林さんおっしゃった道案内とかだったら、何も考えなくても継続することじゃないとわかりますよね。
なんですけど、仕事においてどこまで善意で、どこからが継続性のあることかを見極めるのが、すぐにはできないと思いますので。
善意と仕事の相性



それこそまた本質を見ないといけないなとすごく思いますね。



だから善意を発揮しないと継続できない仕事だったら、仕事として不正確なんですよ。
つまりそれは仕組み化しなきゃいけないんですよね。



なんか気づかずにまた片足突っ込んでしまってそうなお話ですね。



まあこれはあると思いますよ、皆さん。
ちょっと立ち止まって、「 これ善意でやろうとしてるんだけど、次頼まれた時どうすんだっけ 」みたいな話とかまで少し考えてもらうといいのかなと思いますよね。
ただ、仕事を円滑していく中では断りすぎてもダメなんですよね。
だからきちんと会話をして、その人だけじゃなくて、組織の課題として、ちゃんと仕組みとして防いでかなきゃいけないですよ。



これってやっぱ日本人にありがちなもんなんですかね?



僕がビジネスの本を読んでて、それを見る感じアジア圏に多い印象ですね。
ただ、日本みたいに見返りのない善意を求めすぎるっていうところは、ちょっと日本人の悪い癖かなと思いますね。
アジアの多くの国々は、基本的に善意は見返りを求めて提供するものという考え方があります。
だから、善意を受ける側も無料でで善意を受けすぎだったってところもあると思いますね。



善意を金額だとか物に換算することは汚いって思ってる人もたくさんいるわけですけど。
ちょっと奴隷根性が染み付いてるかなと思いますね。



そうですね。
ボランティア精神こそ美しいみたいな。それも本質をちゃんとつく、見抜く力なもんあるんでしょうけどね、大事なものとしては。
まとめ



ということで今日はですね、善意を破綻する。
破綻という表現がまさにドンピシャなお話でございましたがいかがでしょう。



皆さんも善意かどうか分かってなかったら、今のは善意でやってしまったんだろうかっていうのを考えないといけないのかもしれません。
中小企業のDXを加速する「ノーコード」とは?うちの会社でも導入できる?