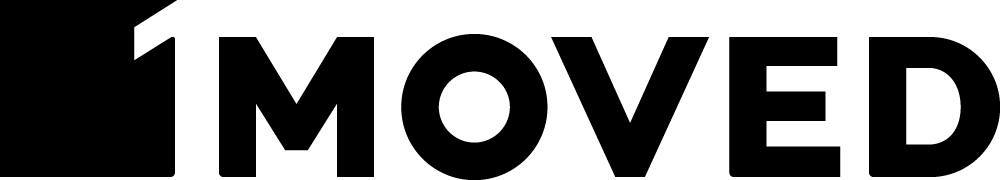理由と言い訳/ハタデザ!ぶっちゃけnight
この記事は「 理由と言い訳 」をテーマにしています。
理由を伝える立場と聞く立場のそれぞれから、どうしたら適切なコミュニケーションがとれるのかを考えます。
ぶっちゃけnightとは
働き方トレーナー・峠 健太郎、プロ雑用・小林 信也が、働くということの本質について語る番組です。
 峠
峠今回のテーマは「 理由と言い訳 」です。
どうしても言い訳してしまう時ってありますよね。
言い訳といえば、学校ネタが定番です。
「 何で遅れたんだ 」「 子猫が迷子になってまして 」
「 言い訳をするんじゃない! 」
というようなシーンを見たことがあるのではないでしょうか。
「 理由 」か「 言い訳 」か



同じことを言っても、人や場面によって「理由」になったり「言い訳」になったりします。言葉の意味は同じなのに不思議ですよね。
自分は理由として説明しているのに、相手からは言い訳としか受け取ってもらえないこともあります。
たとえば、私が毎日遅刻をしていて、その度に「 電車が遅れてしまって 」などと言っていたら言い訳だと捉えられますが、
一回も遅刻をしたことがない小林さんが「 電車が… 」と言ったら、それは理由になります。
同じ言葉でも、これが「 理由 」でこちらは「 言い訳 」だと単純に決められないのです。
感情が入ると言い訳に聞こえる



でも、言い訳に捉えられてしまいがちなシチュエーションはあると思います。
さっき言った通り、遅刻をしたことのない人が初めて理由を言っても言い訳に捉えられないですよね。
けれど、毎日遅刻する人が理由を言っても、自分を正当化するための言い訳に聞こえてしまいます。
自責と他責の問題も関わってきそうです。
言い訳をするときは、「 嫌われたくない 」「 評価を下げられたくない 」という気持ちがあると思うんです。
仕事でミスをした理由を伝えるときに感情が入ってしまうと、言い訳に聞こえてしまいそうですよね。
結局、自分がネガティブな状態になりたくないという理由で発せられる言葉は、言い訳になってしまうわけですね。
許されるかは関係性次第



峠さんが言う通り、理由と言い訳の違いには自責にするか他責にするかが関係あります。自分のことをかばうのかどうなのかって話ですよね。
たとえば、第三者になぜそれが起こったのかを客観的に説明してもらうと、それは本人の言葉ではないから言い訳ではなくなります。
本人が「 遅刻をした理由は寝坊です 」と言って、第三者が「 確かに彼は寝坊をしました 」と言ったら、それは一応理由ですが、何も弁護にはなりません。
言い訳は弁解という意味ですから、自分の口から弁解をするってことは自己弁護になります。
ですから、どのような客観的な理由であれ感情であれ、相手が許すかどうかは、それを投げかけて相手に判断を委ねるしかないんですよね。
だから、客観的な事実を述べたから許されるわけでもないし、自己弁護をしたから許されないわけでもないのです。
結局のところは相手との関係性に依存しているんじゃないでしょうか。
まずは質問に答える



ありがちなシチュエーションで、先輩が後輩に「 頼んでいた資料はできた? 」と聞く場面があったとします。
後輩Aは「 まだです。 」と言います。
後輩Bは「 こういう理由があって、これがこうで… 」と言い、結局どっちなの? と聞かれてしまいます。
後輩Bは、理由として成立しそうなのに、言い訳になってしまっていますよね。
後輩Aもできていない理由を聞かれて言い訳をするかもしれないのですが、最初に事実を持ってくるかこないかで印象はだいぶ変わると思います。



「 資料はどうなっているか 」という質問に対してまず答えを返すかどうかということですね。
後輩Aは答えを返したので、その後に理由を聞かれるんですよ。
でも後輩Bは最初に答えを返さず自己弁護から始めたので、言い訳と捉えられてしまいました。
だから、質問をされたら、まずは適切な返答をするといいですね。
最初に自分が何を求められているのかを理解して答えれば、言い訳ではなくて理由を伝えられます。
正直な人は最初に「 できませんでした 」と言いますよね。
素直さや正直さは、コミュニケーションにおいてすごく重要だと思います。
言い訳は自己の内面的な理由で、客観的な理由ではないんですよ。
言い訳に隠されたもの



事情の原因については、言い訳が重要だったりします。
たとえば、寝坊が多い社員がいて、「 寝坊した 」と何回も言われたとします。そこには客観的な事実も、自己弁護もあります。
なぜ寝坊が続くのかを解きほぐしていくと、仕事を覚えるのが遅いし会社が教育をしっかり出来ていないから、残業が多くなっているという事実が発見されるかもしれません。
僕は、言い訳をするなと言ったことがありません。
どうしてかというと、言い訳をされた時になぜそうなったのか理由を聞くことを繰り返して、事実ベースの事象と感情ベースの事象を全部詳らかにすると、自分で解決できるとだと気づかせることができるからです。
これらは問題解決思考では重要なことです。
しかし、人間関係やコミュニケーションに関してはネガティブな影響が出る場合が多いでしょう。自己弁護を受け取る側の感情としてはイラッとしてしまう。
それ以上話を聞いてもらえなくなってしまうので、まずは自分がやらかしてしまったことを素直に謝ることが大事ですね。
問い方の重要性



それから、問い方も重要です。
「 なぜ遅刻をしたんだ 」と聞くのはあまり有効な解答が返ってくる問い方じゃないんですよね。
多くの人は問いかけの方法を間違えています。だから言い訳が返ってきてしまうんです。
たとえば「 鯨は何類ですか 」と聞いたら、返答の仕方はかなり絞られます。
しかし、「 鯨とは何ですか 」と聞くと、いろいろな返答方法があるので、さまざまな回答が返ってきます。
それに対して質問者が「 そういうことじゃないんだよな 」と言うのはおかしいですよね。
それなのに、このような質問を無意識のうちにしている人が多いんです。
それだと、答える方は結局何を聞かれたのかがわからないのです。



聞く側の質問力がかなり重要ですね。
場合によっては回答がどうしても言い訳になってしまう質問もありますね。
リサーチ力より質問力



少し前までは、情報があふれすぎている世の中では検索力が重要だと言われていましたけど、最近は質問力の方が大事になってきていますね。



AIの活用などに関しても、質問力が重要になってきていますね。



質問力はどうやってつけたらいいんでしょうか。
質問力を上げるには思考力が必要



結局のところ、言葉を表層で捉えないように、思考力を高めるというのがまず第一歩だと思います。
世の中を見渡してみると、入ってきたことをそのまま受け止めてしまう人が多いなと感じています。
入ってきた情報や意見などに対して「 なぜ? 」という問いを持たないということです。
そういう人たちは、誰かの発言に対して表層的にしか理解しようとしていません。
本質を探っていく癖をつけないといけないですよね。
また、それと同時に自分に関係ない問題や話題を無視する「 無視力 」も必要になってきます。



世の中の情報が無限であるのに対して脳内のメモリには限界がありますもんね。
おわりに



今回のまとめとしては「 言い訳される側にも言い訳される理由がある 」ということですね。



「 言い訳されないためには質問力が大事 」という格言たる話がありました。
確かにそうだなと思った方も多いのではないでしょうか。
「 質問力 」を意識していきたいですね。